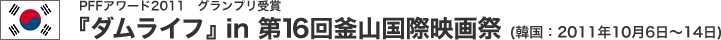No.23:『ダムライフ』in 第16回釜山国際映画祭
日本国内のみならず、海外の映画祭でも上映される機会が多くなったPFFアワード入選作品&PFFスカラシップ作品。このページでは、そんないろいろな映画祭に招待された監督たちにも執筆していただいた体験記を掲載します。

ホテルから見た釜山の街並。

レッドカーペット入口にて。
10月の初め、PFFの表彰式が終わって一週間と経たない頃、僕は今作で録音と整音を担当してくれた、唯一と言ってもよいスタッフの弟と共に、お隣の国、韓国へと旅立ちました。12年振りの海外旅行。犯罪者にしか見えない高校一年の自分が写ったパスポートを、ここ3ヶ月で8キロも太った29歳のアラサー男の写ったパスポートへと更新し、向かったのは釜山国際映画祭。招待部門は、New Currents Awardという国際コンペティション部門。人生初の海外映画祭参加、そして国際コンペ参戦です。この幸運は、PFFが入選作品を海外映画祭に紹介してくれていることによってもたらされたものです。
釜山には、『ほえる犬は噛まない』での追走シーンで用いられたようなマンションがそこかしこに存在します。感動余って「まるで風景自体が映画への情熱を放っているかのようだ。」と独りごちてみましたが、日本語の通じる人がほとんどいないため、一人でしゃべっている変な奴がいる、といった目で見られてしまいました。当り前のことではあるのですが、海外映画祭では、日本語は基本的にほぼ通じません。考えたこともありませんでしたが、それは、僕のように英語を解す能力が著しく低い人間にとっては、とてつもなく怖い状況です。そのため、僕は必然的に、街を歩くだけでビクビクし、映画祭スタッフの方と会うだけでオドオドするようになってしまいました。仕舞いには、オープニングセレモニーの後、別部門で映画祭に参加していた森岡龍監督と行った居酒屋で、大量のお通しが出てきた際に(韓国では大量のお通しがほとんどの店で無料で出てきます)、言葉が通じないせいで頼んでもいないものが大量にきてしまったのではないか、と焦り始める始末です。オープニングセレモニーの間、単独行動をすることになっていた弟に至っては、「どこかの屋台で、一人で夕飯を食べる」と息巻いていたのにも関わらず、ルームサービスで夕飯を済ませ、その後は部屋で携帯電話をいじって平静を装い続けていたということでした。こんなことで大丈夫なのか、と不安ばかりが募る中、初日の夜は更けていきました。
しかし、二日目の昼、勇気を出して電車に乗ってみた時のことです。僕は、日本と同様に、躊躇なくイスに座りました。すると、どういうわけだか、激しい舌打ちの音が辺り一面から聞こえてきます。なんだ、と顔を上げると、僕の前にはお年寄りの方が立っており、その後方に立っている多くの若者は、すさまじい勢いで僕を睨みつけていました。「譲れということなのか?」僕は立ち上がり、おそるおそるお年寄りに席を譲りました。すると、そのお年寄りはニコリと笑い、「カムサハムニダ」と僕に言ってきました。見ると、若者達も少し微笑んでいます。どうやら韓国では、お年寄りの方が電車に乗ると、若者は皆、席をすっと立つもののようなのです(あくまで僕独自の調査によって判明したものです)。それに気付いた時、僕ははっとしました。「そうか、ここにいるのは、みんな優しい人達なのだ。気にすることなど何もないのだ。僕は何をビクビクしていたのだ!」そうです。僕はこの国で、いや、この世界で、堂々と生きていてもいいのです!その時から、僕は臆することなく、前を見て、堂々と釜山の街を歩くことができるようになりました。

女子中学生との記念撮影。
しかし実際、堂々と振る舞わなければ、言葉の通じない海外では何一つやっていくことはできません。これは釜山に限ったことかもしれませんが、韓国の方は、質疑応答時も率直かつ大量に質問を投げかけてきます。それに対して、言葉も通じないのに曖昧な態度で臨んでいては、何一つ相手に伝えることはできません。しかし、はっきりと、ある意味でかい態度で、確実に回答をすれば、ちゃんと思いが相手に届き、コミュニケーションがそこに成立します。僕も、数十人の女子中学生が見に来てくれていた際に、質疑応答で「全く意味がわからなかったんですが、この映画は何なのですか?」と聞かれましたが、堂々と「意味がわからない時間を過ごさせてしまってごめんなさい。でも、僕はあなた方のような若い方々に今日、映画を見てもらえて本当にうれしいです。ありがとうございます」と言い切ってみたところ、その女子中学生らに囲まれ、サイン攻めにあうことができました。実際のところは、これは韓国が、僕のような無名の者であっても、監督というものがそもそもスターである、という文化であったために起こった現象に過ぎないのですが、僕はもう完全にその場では勘違いしてしまい、「俺は今、モテまくっている。今という時よ、永遠に続いてくれ」と思ってしまいました。しかし、現実というのは残酷なもので、そんな魔法のモテ時間が適用されるのは、上映会場の中だけでした。会場を出ると、僕はいつもと変わらぬ、ただの無名で背の小さい29歳の男なのです。もしかしたら、と考え、監督であることを示すパスを首にぶら下げたまま電車に乗ったりもしてみましたが、やはり何の効果もありませんでした。
また、数回の上映を通して他に感じたこととしましては、堂々と振る舞わなければならないのは、監督だけでなく、作品内の登場人物もなのだ、ということです。言葉が通じず、また、文化も異なる海外においては、登場人物の行動や心理がはっきりと示されていなければ、観客から好ましい反応は得られません。実際、日本では全くウケなかった、作品前半の割とはっきりとした笑いのあるシーンが韓国では最もウケ、日本で最もウケた、作品後半のスプラッター的なシーンを笑いにするという少しわかりにくいところを付いた部分は、韓国では全くウケませんでした。世界に向けて何かをするためには、言葉だけでなく、シーンのつくり方など様々な部分で、「はっきりと何かを提示し、わかってもらおうとする」姿勢が必要になってくるのだな、と感じました。というわけで、とにもかくにも、海外においては、堂々と振る舞うことが非常に大切であると、僕は感じたのです。

(左から)熊切監督、北川監督、アミール・ナデリ監督。

クロージングセレモニーの様子。
釜山では、毎夜のようにパーティーや飲み会がそこかしこで開かれています。しかも、どれもお金はかかりません。勢いづいた僕は、臆することなく様々なそういった催しにも参加してみました。そういった場には、釜山だけでなく、他の様々な映画祭の方々、そして、監督らがいらっしゃっていますので、そういった著名な方々とお話をできるのも、こういった映画祭の素晴らしいところです。僕も、様々な方々とお話させていただきましたが、監督や俳優の方ですと、アミール・ナデリ監督、熊切和嘉監督、イ・サンウ監督、吉野耕平監督らとお話させていただき、また、キム・コッピさんとお話をして握手をさせていただきました。どの方も素晴らしくいい方ばかりでしたが、特に感動したのはコッピさんです。コッピさんは、まさに絶世の美女といった感じであった上に、握手させていただいた手は、絹と錯覚するほどにやわらかいものでした。ですから、握手をさせていただいた瞬間、「しばらくは手を洗わないでおこう」と思ったのですが、酔っていたので忘れてしまい、部屋に戻って速効で風呂に入ってしまいました。鼻歌を歌いながらご機嫌に風呂に入っていたあの時の自分を思うと、悔しくて、今でも壁を一、二発殴りつけたくなります。
少し話が変わってしまいますが、釜山のメイン会場となる映画の殿堂はとてつもなく大きな会場です。花火なども交えたド派手な演出で、オープニングやクロージングセレモニーでは、その会場が華やかに彩られます。しかし、すさまじく大きな会場ですので、お会いしようと思っていた方にお会いできないことも多々あります。今年のPFFで最終審査委員をやられており、僕に賞を授与してくださった塚本晋也監督が登壇されていた際などは、ぜひともご挨拶をと壇上付近にうかがったのですが、とてつもない量のファンの方に囲まれておられ、収拾がつかず、結局ご挨拶できませんでした。また、クロージングセレモニーの際などは、さらにすさまじい数の観客と関係者が訪れますので、僕のような場慣れしていない人間は、どの係員の方に従えばよいのかもよくわからなくなります。実際、僕は入場の際に、間違った係員の方の誘導に従ってしまい、「こっちだ、こっちだ!」と言われた先に行くと、そこは観客席で、戻ろうとした時にはもう僕の出番は終わってしまっており、結局レッドカーペットを歩くことができませんでした。一応、僕の出番付近の時に係員の人に“I want to go there!”みたいに言いはしたのですが、「いつか俺もあそこに行ってやる!」みたいに言っている野心溢れる奴のようになってしまい、うまくいきませんでした。しかし、今は、本当にいつかまた行ってやればいいじゃないか、となんとか自分を納得させてはいます。
クロージングセレモニーでは、レッドカーペットを歩けなかっただけでなく、残念ながら受賞もできず、悔しい思いをしましたが、セレモニー後に開かれる、クロージングパーティーの際に、そんな悔しさを吹き飛ばす、嬉しい出来事がありました。審査員の一人として参加されていた、オダギリジョーさんとお話する機会を得たのです。間近で拝見したオダギリジョーさんのかっこよさたるや、もうこの世のものとは思えないほどで、また、何と言いますか、オーラのほとばしり方のようなものも半端ではありませんでしたが、お話させていただくと、非常に穏やかな方で、本当に親身に様々な感想を言ってくださいました。いつかきっと、何かの作品でご一緒できるよう今後も頑張ろう、と強く思いました。
長々と書いてきましたが、今回の旅は本当に僕にとって、貴重な経験となりました。海外へ行くということは、よく言われることではありますが、自分というものを客観視することができるようになるだけでなく、自分というものに自信を持ち、また、もう一度あそこに行きたい、と思えるという意味でも、新たにまた何かをつくろうという意欲を湧かせてくれるよい機会であったと感じています。今後も、今まで以上に頑張って、また釜山に行きたい、と強く感じました。
今回、釜山に行くことができるきっかけとなった作品を、僕と一緒に、頑張ってつくってくれたスタッフ、キャストの方々、そして、海外に僕の作品を紹介してくださったPFFの方々に感謝します。ありがとうございました!
文:『ダムライフ』監督 北川 仁