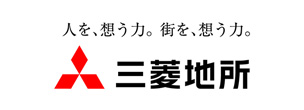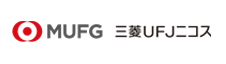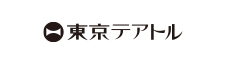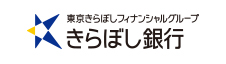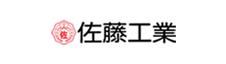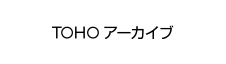一般社団法人PFF Overview
一般社団法人PFFとは
「ぴあフィルムフェスティバル(PFF)」は、1977年、ぴあ株式会社が東映大泉撮影所で開催した「第1回ぴあ展」でその産声を上げました。以来40年以上にわたり、世界でも類を見ない自主映画のコンペティション「PFFアワード」をメインとした映画祭を開催し、これまでに190名を超えるプロの監督を輩出しております。また、新人監督の長編映画製作システム「PFFスカラシップ」でPFFアワード受賞者の次のチャンスを創生し、その活動の幅を広げてまいりました。
そしてスタートから40年を迎えんとする2017年4月に、PFFの活動をより公共的な事業として、官民を含めた社会全体で事業の継続と発展を支えることのできる環境を作るため、ぴあ株式会社、株式会社ホリプロ、日活株式会社のPFFオフィシャルパートナー3社が中心となり、「一般社団法人PFF」を設立いたしました。
一般社団法人PFFは、「映画の新しい才能の発見と育成に係る事業を通して、映像文化の発展に寄与すること」を目的として掲げております。新しい才能を紹介する映画祭「ぴあフィルムフェスティバル」の開催、新しい才能の発見をテーマとした「PFFアワード」の授賞、新しい才能の育成を目指した「PFFスカラシップ」による新作映画の製作と公開、さらに新しい才能の国際的な飛躍を後押しすべく新設した映画賞「大島渚賞」などの事業を通して、映画の新しい環境作りを担ってまいります。なお、ぴあ株式会社からは、PFFを将来にわたって安定的に運営していくことを目的とした10億円の基金の拠出を受けております。
理事長挨拶
事業概要
活動

「ぴあフィルムフェスティバル」の開催
「ぴあフィルムフェスティバル」は、「映画の新しい才能の発見」をテーマに1977年にスタートした映画祭です。
観る機会の少なかったインディペンデント映画の面白さを広く伝えることを目的として、世界でも珍しい自主映画のコンペティションである「PFFアワード」と、若い映画監督の刺激となるような国内外の多彩な映画のプログラムなど、映画祭ならではの企画を続け、若い映画の作り手やファンが集う場所となっています。

「PFFアワード」の実施
募集時より1年以内に完成した自主映画であれば、年齢、性別、国籍、上映時間、ジャンルなどを問わず、すべてが自由な自主映画のコンペティションです。
応募作品は4ヵ月に及ぶ厳正な審査を経て入選作品が決まります。入選作品は「ぴあフィルムフェスティバル」で上映され、その中からグランプリ他の各賞が授与されます。46回の開催までに、25,616作品が応募され、777作品が入選しています。入選者の中からは、プロの映画監督として活躍する人たちが190人を超え、若く新しい才能の登竜門として広く認知されるようになりました。

「PFFプロデュース(旧称:PFFスカラシップ)」の実施
PFFが制作から公開までをトータルプロデュースする長編映画製作システムです。
毎年のPFFアワード入選者の中から、自分たちの作りたい映画企画の提出を受け、選考を経て1人が選ばれます。選出された監督は、専任プロデューサーとマンツーマンの体制でじっくり時間をかけて、企画開発から公開までの映画の全プロセスを体験します。1984年の第1回から2024年までに製作された作品は29本になります。

「大島渚賞」の授賞
「大島渚賞」は、2019年度に創設した新たな映画賞です。日本で活躍する若手監督を対象に、映画の未来を拓き、世界へ羽ばたこうとする、新しい才能に対して贈られます。かつて、大島渚監督が高い志を持って世界に挑戦していったように、それに続く次世代の監督を期待と称賛を込めて顕彰します。2025年の第6回は『ナミビアの砂漠』の山中瑶子監督が受賞しました。

「放送・配信」による視聴拡大
様々なチャネルで自主映画に触れる機会を提供しています。「U-NEXT」では定額制配信にて、現在240本以上の「PFFアワード」入選作品が視聴可能です。またTOKYO MXとチバテレビミライチャンネルでは月替わりで入選作品をテレビ放送、2024年の5月からはJALの国際線・国内線でも機内上映されています。
さらに、今春からは新しい配信プラットフォーム、Roadstead(ロードステッド)にてデジタルコレクション販売も開始しました。

「PFFデジタルアーカイブ」の推進
「自主映画」という日本独自の映画文化を保存して次世代に伝えるために、過去の「PFFアワード」入選作品をデジタル化しています。600本を超える入選作品の約半数となるビデオ作品のデジタル化は既に終了し、現在は1990年代の貴重な8ミリ・フィルム作品のデジタル化を本格的に進めています。また、2023年からはデジタル化した自主映画の名作を映画祭でも特集上映しています。
理事・監事
(2024年6月現在)
| 理事長 | 矢内 廣 |
|---|---|
| 副理事長 | 堀 義貴 |
| 常務理事 | 松井浩之 |
| 理事 | 五十嵐 博/矢嶋弘毅/木戸文夫/荒木啓子/石川 毅 |
| 名誉理事 | 林 和男 |
| 監事 | 能勢正幸 |
会員一覧
(2025年6月現在)
基本情報
| 名称 | 一般社団法人PFF |
|---|---|
| 住所 | 〒150-0011 東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー 地図 |
| お問い合わせ | info@pff.or.jp |