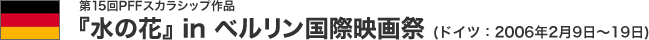No.4:『水の花』in ベルリン国際映画祭
日本国内のみならず、海外の映画祭でも上映される機会が多くなったPFFアワード入選作品&PFFスカラシップ作品。このページでは、そんないろいろな映画祭に招待された監督たちにも執筆していただいた体験記を掲載します。


上映終了後、花束で歓迎される木下監督。
© Max Kullumann
『水の花』がベルリン国際映画祭に出品が決まったとプロデューサーからメールがあったとき、私はレンタルビデオ屋でバイトしていた。敬愛する監督達と同じ時間を共有できる、そして何より『水の花』がそこで上映される。夢のような話である。
『水の花』の上映自体は映画祭の後半5日間に集中していたが、せっかくの映画祭、観ない事には始まらない、と10日間ベルリンに滞在した。しわくちゃになった上映プログラム片手に、次の会場へ次の会場へと、監督だろうと、プレスだろうと、一般市民だろうと関係のない渦の中、競う様にして走った。
『水の花』が出品されているキンダー部門のオープニング作品「Opal Dream」を観る。良質な児童映画である。監督は『フル・モンティ』など多くの映画を撮ってきた方らしい。同じコンペの上で、同列に扱い、日本で見た事の無いような巨大な劇場で上映する。何て器がでかい映画祭だ。
上映後、ロビーにいたディレクターのThomas Hailer氏に挨拶すると、開口一番「ゴージャス・フィルム!」と、強く握手を求めてきた。大きな体をしているが、子供の様に表情豊かな人である。日本で『水の花』に「豪華な」「華麗な」といった形容詞を聞く機会があまり無かったので、とても新鮮で、最高の褒め言葉のように感じた。
上映前日『水の花』が上映されるのだと実感がわいてくる。と、ともに日本においてきたはずの曖昧な不安がじわっとよぎる。
『水の花』は私の中で色々な意味で挑戦作である。自主制作とは訳が違う、毎日が修行のような日々の中、プロのスタッフの方たちと一緒に作って行った。前作『鳥籠』の姉妹作とも言われるが、今回は意図もあって、フィルムによる長回しを多用した、ほぼ1シーン1カットと、前作と全く異なった方法で物語を紡いでいった。映画の伝えんとしていることが変われば、それにふさわしい伝え方を選択するのは当然と考えるが、全く不安が無かったと言えば嘘になる。
どういった反応になるのか全く想像がつかなかったが、上映が始まると同時に不安は消え去った。外国の観客は日本の観客に比べて、素直に大きく感応してくれる。まるで映画と対話しているようだ。また、私が意図していないところで、大きな反応があったりと自分の映画を再発見する機会ともなった。映画とは観る者が想像(創造)をめぐらせ、参加する事によって完成すると考える。作り手冥利に尽きる場であった。映画は大きな拍手に飾られた。

会場にて、子供たちにサインを求められる大人気の木下監督。
Q&Aは「美奈子役、優役の子はどうやって決まったのか?」「普段はどんな生活をしているのか?」と子供らしい素朴な疑問や、映画で描かれるラストに関する鋭い質問があったりと、多くの質問があった。終了後、サインを頼まれる。普段サインを書く機会がない私は「木下雄介」と書くしかなかったが、漢字が思いのほか珍しいらしく喜んでくれた。
帰国後にある上映を一度残して、私のベルリン国際映画祭は終わろうとしていた。『水の花』のラスト、美奈子は道の先をじっと見つめる。映画は終わるが、新しい美奈子の物語が始まるのだ。この先も私の道は続いている。とにかく撮り続けよう、と強く思った。
と、すっかり夢に浸かっていた私は、まんまと帰りの飛行機に乗り遅れてしまった。空港の人皆に呆れた顔をされながら、本来帰国後で行けない事になっていた、3回目の上映の舞台挨拶に行けることになったので、映画祭に連絡をお願いし、急いで向かった…。
文:『水の花』監督 木下雄介