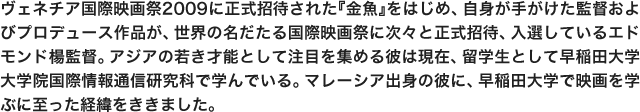
――早稲田大学大学院国際情報通信研究科に来る前に、オーストラリアで映画制作を学んでいたと、おききしました。まず、自国のマレーシアではなく海外で映画を学ぼうと思ったきっかけを教えてください。

「父親が映画の批評家、母親が歌手だった影響からか、小さい頃から映画に親しんでいて、いつからか将来は“映画監督になりたい”という意志を抱くようになりました。ただ、昔に比べると増えてはいるのですが、マレーシアにはこの早稲田大学大学院国際情報通信研究科のような映画を専門に研究する大学は少ない。映画が専門的に学べる場が少なく、選択肢があまりないというのが実情です。また、マレーシアは残念なことに東南アジアで唯一映画祭のない国。おそらく一般的なマレーシア人は映画祭をイメージすることさえできないと思います。ここから察しがつくように、映画界が活況とは言い難い。さらに言うと、マレーシアの場合、作られるのはあくまでビジネスを目的とした商業映画がほとんど。いわゆる日本で言うところの芸術性の高いアート映画が作られ、上映できるような環境にもありません。自国の映画を海外マーケットに向けて発信していくといったことにも積極的ではない。そういう状況がありまして、自分としてはもっと広いビジョンを持って映画を学びたいと思い、海外を選択しました。」
――それで、まずはオーストラリアへ渡ったわけですが、そこから早稲田大学大学院国際情報通信研究科入学に至った経緯を教えてください。

『金魚』を演出するエドモンド楊監督(写真中央)
「オーストラリアの大学では文学と映画のマネジメントおよびマーケティングの方面を学びました。文学を学ぼうと思ったのは、シナリオを書くのに非常に勉強になると思ったからです。一方、マネジメントおよびマーケットは、プロデューサーとしての勉強をすることで映画をもっと広い視野で見られると思いました。映画の全体像を見ることで、自身の夢である映画監督になることも近づけるとともに、映画を別角度から考えることもできる。そう思い、マネジメント方面からまずは映画を学びことを選びました。で、次のステップに進む時期を迎えたとき、それまでは西洋的な文学や文化を学んでいましたから、今度は東洋的かつ自国のマレーシアを含む東南アジア的文化といったものをもっと学びたいと思うようになりました。また、それらを自分の中で消化し、反映してなにか独自の作品がつくれないかと思ったんです。同時に僕は日本の映画や文学、文化がすごく好きで興味がありました。そんなとき、日本の文部科学省に奨学金制度があることを知って、早稲田大学大学院国際情報通信研究科に進むことを決めました。」
――現在まで在学して、ご自身にとって早稲田大学大学院国際情報通信研究科はどんな場所になっているでしょうか?
「自分が留学生ということもあるのでしょうけど、日本の文化をはじめ様々なことにインスパイアされることが多くて。自分でも驚くぐらい、いろいろなアイデアが生まれるようになりました。今はとにかく映画を作りたいと思う衝動に駆られる毎日です(笑)。これはもちろん日本での経験は大きいのですが、早稲田大学大学院に身を置いていることも大きいと思います。というのも、早稲田大学大学院国際情報通信研究科は、その自分の案を具体化、作品として実現化できる場所でもあるんですね。ありがたいことに、当初から、安藤鉱平教授をはじめ、ほんとうにいろいろな方がサポートしてくださって、自分の研究テーマを軸に、自身による創作を自由に作れる環境がある。早稲田大学大学院国際情報通信研究科は、やる気さえあれば、いつでも自分の創作に挑むことができる場所です。僕はとにかく毎日毎晩研究室に入り浸り(笑)、作品制作に挑む日々が続いています。」
――今、研究テーマとの話しが出ましたが、それを少し教えていただけますか?

「僕の研究テーマは“マジカル・リアリズム”。ラテン・アメリカの作家、ガルシア・マルケスらが使っている言葉なのですが、日本語直訳すると“魔法現実”(笑)で、ようは現実とイリュージョンが交差するとでもいいましょうか。例えば、自分の心の中で思ったことが、実体となって現れたり、または死んだはずの人が目の前に現れたりといったこと。こういった世界観はマレーシアにもある。いろいろな文学や文化を学ぶ中から、僕は今、南米文化と東南アジア文化がひじょうに近いところがあるように考えています。また、日本に来て川端康成や谷崎潤一郎、寺山修司といった作家の作品に触れて、そこにもどこか共通性を見い出しました。それらから大いにインスパイアされて今、“マジカル・リアリズム”をテーマかつ表現した映画作品を撮り続けています。もし、来日して日本の文化や文学、映画に触れていなかったら、自分はこういう題材に思いを巡らせることができたか分からない。映画作家としての個性ともいうべき、オリジナルな創作に至れたかも分かりません。それぐらい日本であり、早稲田大学大学院での経験は大きい。実は来日前に作った作品があるのですが、これは完全なコメディ映画。たぶん今の僕の作品を知る人が観たら、まったく想像すらできないでしょう。当時は自分の進むべき映画作りを模索していた時期でした。それが日本でありこの研究室に来て、いろいろな刺激を受ける中で、自分の進むべき方向が見えたところがあります。」
――早稲田大学大学院国際情報通信研究科で最初に制作した『手紙』も、ヴェネチア国際映画祭2009に正式招待された『金魚』も川端康成が原作ですね。これもやはり日本であり早稲田大学大学院で学んでいなかったら、生まれていなかった?

「そうですね。どちらも、今まで蓄積してきた自分なりのモノの見方や経験に、早稲田で得たことが加味されて出てきました。日本に拠点をおく今の自分の環境から生まれてきた作品といっていいと思います。あと、映画監督を目指すひとりの人間としては留学も大きな経験になっています。というのも、留学生活を経験することで、客観的に母国・マレーシアのことを見られるようになりました。自国にいるとなかなか見えてこない、日本にいるからこそ見えてくるマレーシアの真実であり真髄に気づかされました。ある意味、ひじょうに冷静かつ客観的な視点で自国であるマレーシアのことを語り、描くことができるようになりました。物事を画一的に見ないで多角的に見る、映画作家としての視点が養われた気がします。また、外国人としてここ日本にいることで体感する寂しさや悲しみ、これもまた大きな経験。やはり体験者だからこそ描ける、本当の悲しみや寂しさがある。こういったことも現在、日本に拠点をおき、自身の映画作りをあれこれ考えられる早稲田大学大学院の環境があるからこそ表現できるようになったと思います。」
――撮影技術や演出手法など、実践的なことで体得できたことはありますか?


「僕の場合は、自分の作品の現場で体得していっている感じです。この実践こそが今後のための大きな力になっていますね。もちろんシナリオを書いたら、教授からいろいろとアドバイスをいただけますし、ほかにもいろいろとサポートはしてくださいますので、それも大きいのですが。あと、僕は日本のスタッフともマレーシアのスタッフとも仕事をしている。日本の現場もマレーシアの現場も経験しているわけですが、これが同じアジアでもまったく取り組み方が違うんですね(笑)。日本のスタッフはすごくプロフェッショナルでひじょうに細かいところまでこだわり作り上げていく。完成図のあるシーンがあったら、それに向かいきちんと手順を踏んで、一切の妥協許さない完璧な画を作り上げようとする。でも、それゆえ融通がきかないというか、急な変更やハプニングへの対応が苦手で、そういったことをあまり良しとしない。マレーシアのスタッフは良い意味で大雑把。あまり細かいことを気にしない(笑)。でも、その分、急な変更や予定外のことがおきても、フレキシブルに対応する能力がある。例えばマレーシアだったら晴れのシーンを想定していて撮影当日雨降りだったら、じゃあ、雨でどうにかシーンを成立させられないかみたいなことになっていく(笑)。でも、日本だったら当然晴れるのを待つ。そういった具合に違うんです。この異なる現場を体験できているのは非常に大きい。それぞれに撮影や演出するに当たって毎回新たな発見があるんです。例えばどうもうまくいかないシーンの問題を現場で洗い出し対処して、新たな発想や構想のもとで創作するようなこともできるようになった。これは監督として今後歩むに際してすごく大きな経験になっていくと思います。教授のみなさんも実践主義で。映画を作ることが何よりも力になると考えておられて、応援もしてくれるので、それも心強いです。」
――ちなみにエドモンド監督のような留学生は現在どれぐらいいらっしゃるのですか?
「たぶん全体の1/3ぐらいが留学生だと思います。チェニジア人の留学生など、いろいろな国の学生がいます。ただ、別に留学生と日本の学生という線引きみたいな感覚はありません。あくまで同じ映画作りを目指す人間といった感じ。互いが刺激をもらい、与え合う存在です。」

『金魚』ポスター
――今も次々と作品を作り上げているそうですが。
「先ほども話したとおり、とにかく今は1本完成すると、もう次にとりかかりたくなってしまう(笑)。」
――失礼な話ですが、どれも低予算でなかなか作るのが大変だと思うのですが?
「よくそう言われるのですが、そんなことはないです。例えばヴェネチア国際映画祭2009に正式招待された『金魚』はたった4日間の撮影で完成させた作品。みんな低予算映画というのですが、マレーシアの低予算映画を知る僕からするとビッグ・バジェット(笑)です。また、僕はプロデューサーをするとき(2010年に制作した『タイガー・ファクトリー』で彼はプロデュースを担当した)もありますから、無駄なお金は一銭も使わないし、許しません(笑)。僕は低予算でも高品質の映画ができると思っています。優れた映画かどうかに予算は関係ない。そのことを実証するような低コストでも人の心に届く作品を作っていきたいと思っています。」



――もう実証されていますね。これまで発表した作品の数々はほんとうに海外の映画祭で高い評価を受けています。2010年制作のプロデュース作品『タイガー・ファクトリー』と監督作『避けられない事』は東京国際映画祭2010アジアの風部門で審査員特別賞に輝いています。『避けられない事』は釜山国際映画祭2010の短編部門でグランプリにも輝いている。その後に発表した篠原ともえと杉野希妃を主演に迎えた『避けられる事』もロッテルダム国際映画祭2011に正式招待されるなど、数々の国際映画祭で反響を得ています。変な話、海外映画祭への戦略とか綿密に練っていたりするのですか?
「これがまったくないんですね(笑)。よく安藤先生にも“戦略もってみては”とアドバイスされるのですが、僕にとっては常に最新作がベストなので、これは“半年後の映画祭を狙ってとっておく”とかあまり考えないんですよ。その間に新たな作品を作り上げてしまう可能性もあるので(笑)」
――もう、次の作品は出来ているのですか?
「『最後の欠片(原題:Last Fragment of Winter)』という作品が最新作です。この作品の出発点は何気ない風景でした。新宿に出かけたとき、古いカメラをもった女の子の姿を見かけて。その姿に、僕はとにかく心をひかれたんです。そこからインスパイアされてひとつの物語が出来上がり、白川郷の冬季ロケで撮りあげました。これから映画祭に出品予定です。」
――最後に、これから大学院を目指す人にアドバイスがありましたらお願いします。
「映画に対して情熱があれば大丈夫。とにかくその気持ちさえあれば、安藤教授をはじめとした方がバックアップもしてくれますし、自分の目指す創作が存分にできると思います。自分にとっての映画作りをきっと見つけられる場所になると思います」
(2011年11月28日 取材:水上賢治)





