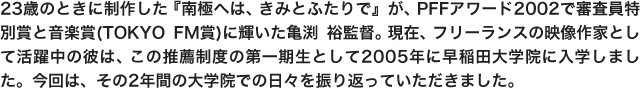
――早稲田大学とPFFの連携によるこの推薦システムがスタートしたのが2005年のこと。亀渕さんのPFF入選が2002年ですから、受賞から数年が経っていました。このころというのは、ご自身はどういった活動をしていたのでしょうか?

「もともと僕は美術大学在学中にコンピュータを使った表現全般を学んでいて、その中で映像に興味をもつようになったんです。そこで映像の世界をちょっと突き詰めていく方向になったんですけど、その過程で知り合う大抵の大人が“映像をやるんだったら、やっぱり映画だよね”的なことを言う。なんだかわからないけれど、数ある映像表現の中でも映画は特別視されている。それに対して、当時、僕は“映画ってそれほど特別なものなの?”とちょっと反感を抱いたりして(笑)。でも、実際に手がけてみないと本質は見えてこないし文句も言えない。それがきっかけで映画を作ってみようと思ったんです。そういう経緯もあるので、映画に対してはある種いじわるというか、どこか冷めた目でみている部分がある。だから、PFFで受賞したときも、もちろんうれしかったんですけど、もうボケッとしたもんで(笑)。“これを次につなげよう”みたいな野心はぜんぜんなかった。というか、そういう野心が世の中に存在することに気付いていなかった。ただ、この受賞の時期前後に出会った方たちから、運良くちらほらと映像関連のお仕事をいただけるようになって。自然な流れに身を任せていたら、いつの間にやら映像業界の中で働くようになっていったのが2005年でした。そして、正直なことを言うと、このころは映像作りに対する意欲がどんどん失せている時期で。やる気がないわけではないんですけど、映像制作に対して真摯な態度で挑めず、どこか機械的な形でしか向き合えない状況になっていました。」
――そんなときに、PFFの方からこの大学院の案内が来た感じですか?
「そうですね。個人的な創作活動はもちろん行なっていましたが、仕事としての“映像作り”自体への興味が薄れつつあって、これはイカンよなあ、どうしよっかなあ…と思っていたときに、このご案内をいただきました。で、ちょうど、僕自身、どうにかこの状況を好転させるには、もう一度、映像というものと、じっくりと向き合う時間が必要だと感じていたんですね。そう考えていたときだったので、この大学院の案内はまさに“渡りに船”で。PFFが学費を半分負担してくれるというのもあって入学を決めました。」

――入学して有意義な時間は過ごせましたか?
「ひじょうに濃い2年間を過ごすことができました。自分なりに学んだことや経験がありましたから、例えば映像編集などのコンピューター関連の知識やノウハウ、カメラの撮影技法といったもののカリキュラムは若干復習みたいな感じではあったんですけど、それを含め、改めて映像というものにきちんと向き合う時間が持てて有意義でしたね。映画、映像に関する資料や機材が揃っていましたし、時間的な余裕ができたということと合わせて、僕にとっては求めていた環境なわけで。ものごとについてしっかりと考え、悩むことのできる、大変幸福な時期でした。」

――ご自身の中で、大きな収穫はありましたか?
「映画を含む、映像コンテンツのビジネスの側面を見ることができたのが個人的には大きかったです。当時も、映像の仕事を生業として、それでお金をいただいて生活していたわけなんですけど、どこか自分の中でビジネスとして映像制作をみていないところがあった。好きだからやっているんだ、という気分が圧倒的に勝っていて、お金は二の次という意識がどっかにあったんですね。まあこれはいまだにあるんですけれども。で、大学院を通じて映画製作の現場を経験したり、その中で様々な人と出会う中で、その割合に変化が出て来た。それはイコール、映像ビジネスの構造を知ってしまうことでもあって。28歳にして、世に出ている大抵の映画が、ビジネス目的で行なわれているのだということに気づきました(笑)。“良い意味でも、悪い意味でもお金を儲けないと次はない。商売という目でみれば作品の評価は数字がすべて”。そんなシビアな映画業界のビジネスの側面を目の当たりにしたことで、遅ればせながら映画業界の現実を知りました。(笑)。たぶんおおよその人は高校生ぐらいで気づいているような気もしますが(笑)。」

――在学時、周りにいる人もやはり映像関係で生きていこうという人が多かったと思います。これはやはり刺激になりましたか?
「制作者を目指している人ほど、刺激を受けることは多いと思います。大学院という学校であるんですけど、学生同士というよりも制作者同士としていろいろな意見交換ができるんですよ。大学院を通じてプロの現場に入る人も多いですから、そういう人からその経験を聞けたりもする。それはやはり否応なしに刺激は受けますよね。」
――今も安藤教授の研究室に残っているとのことですが?
「客員研究員というのがありまして。安藤研究室で制作する作品のお手伝いなどなど、ようは安藤先生の助手をしています(笑)。そのかわりというわけではないんですが、研究員ですから学校にある機材を自由に使えたりします。月に1回ぐらい顔を出す程度なんですけど、大学院と卒業後もつながっていられるのは僕にとっては大きい。安藤先生をはじめとする講師の方とお会いする機会をもてますし、若い人たちとおしゃべりすることで、そこから得られる何かは、大変意義のあることと考えています。」
――今後、目指す入選監督にアドバイスがあったらお伺いしたいのですが?

「そんな偉そうなこと言える立場ではないですよ(笑)。ただ、僕自身はいい時間がもてました。入学したときが27歳で、卒業したときが29歳。社会人生活を送ってからのこの時期に、さらに新しい種類の経験ができたことは間違いなくプラスだったと思います。映画ビジネスの知らなくてもよかった現実を知りすぎたマイナス面もちょっとあったりするんですけどね(笑)。もし、これがもう少し若い大学卒業してすぐの時期とかだったら、これほど吸収できなかった。とくに僕の場合さっきもお話したように、若い頃は…まあいまでもボーッとしてはいますが、若い頃はもっとハードにボーッとしていたのでなおさら。映像制作者としてある程度キャリアを積んで、ちょうどひとつの壁のようなものにぶつかったときだったから、充実した時間をすごせた気がします。」
――駆け出しの時期を過ぎたぐらいの人の方が特に大きなものを得られるのではないか? そういうことでしょうか?
「そうですね。駆け出しのころは、がむしゃらで自分の思いひとつで突っ走れるところがある。でも、そこを通過したとき、多くの困難に直面する気がするんですね。そういう時期に差し掛かった人ほど、得るものが大きいと思います。あと、ひとつ言わせていただくと、“学ぶ”という受け身の姿勢でいると何も得られないで終わってしまう。自分から何かを得ようと思って動かないとダメ。でも、自分で“これをやってみたい”と思って動けば、それを実現できるチャンスを必ず作ってくれます。自分がやりたいことを明確に意思表示した方が絶対いい。そうすれば、安藤先生をはじめ講師陣も必ず力になってくれます。」
――大学院を出て、3年ほど経つわけですが、今はどういった日々をお過ごしですか?
「大学院での2年間で、どうにかリセットでき(笑)、映像の仕事を今も続けています。プロモーションビデオやネット・ドラマなど、いろいろな映像作品を手がけていますが、もちろん、映画もまたやりたいですね。いま目の前にあるすべきことを、ゆっくりとでも一生懸命こなしていくことが結果的に次につながっていくと思うし、前に読んだ本に『“どう”やるかよりも、“ただ”やることだ』ってあって、本当にそうだ、それを継続していくことのほうがずっと重要だ、と心に深く感じた。だから先のことは考えないようにしているんですけど、在学中に学んだこと・考えたことを活かして、なにかこう明るく、その時の自分なりに納得できる結果を求めていけたらと思います。」
(2009年12月24日 取材・写真:水上賢治)





